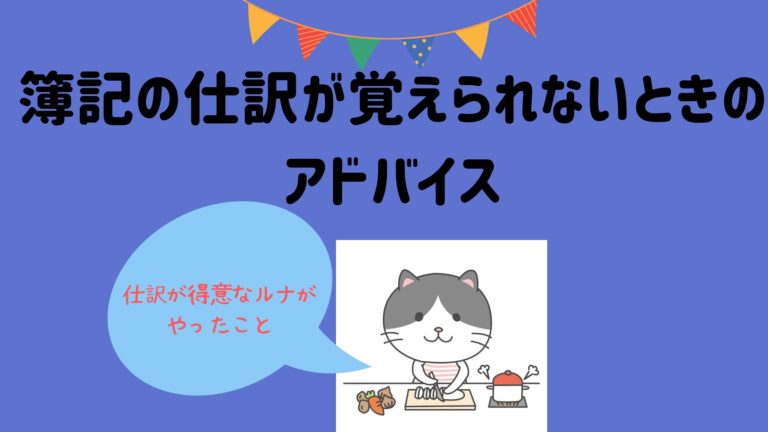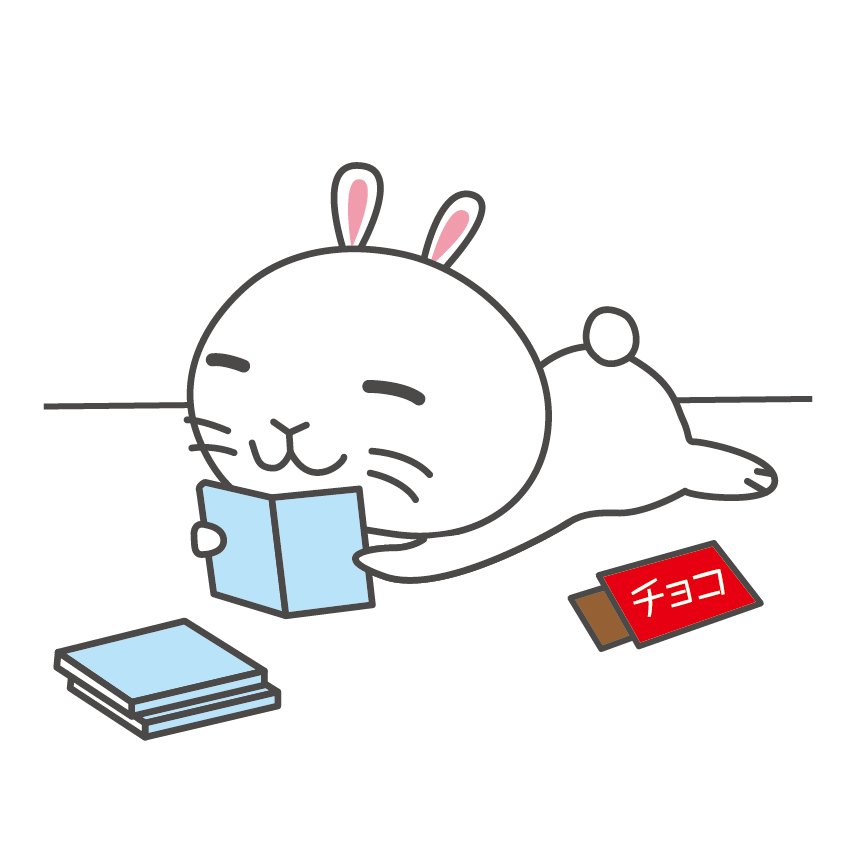
簿記の仕訳が覚えられない!
勘定科目の暗記もできない…どうしたらいい?
こんな疑問に私自身の経験を踏まえ、お答えします。
仕訳を制するものが簿記を制するとは聞くものの、たくさんの勘定科目や仕訳を覚えるのって苦労しますよね。
仕訳や勘定科目が頭に入っていないと、やはり簿記検定合格は難しいです。
仕訳を制することが合格への近道なのは本当です。
私は、2018年11月合格率14.7%の第150回日商簿記2級を受験。
96点(仕訳1問間違い)で一発合格。
その後、未経験経理事務に再就職しました。
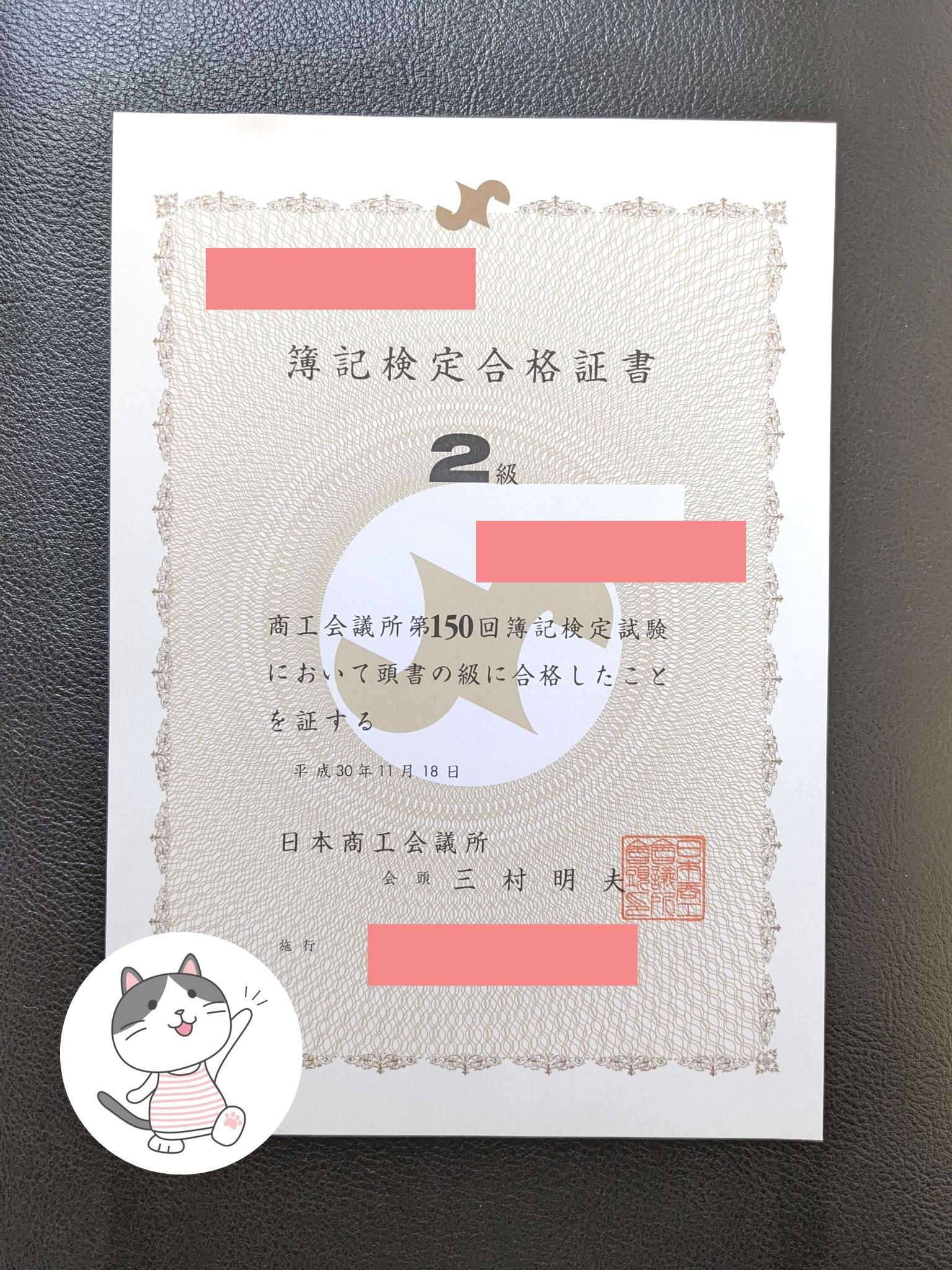
私は簿記3級受験のときから、割と仕訳や勘定科目を覚えるのは得意な方でした。
簿記2級の勉強に入ってからは、勘定科目や仕訳が増え、多少苦労したものの、それでもスムーズに覚えることができていました。
「どうしたら仕訳を覚えることができるのか」
私なりのアドバイスをまとめます。
今月の割引キャンペーン
簿記の仕訳が覚えられないときのアドバイス!【簿記一発合格者が教える】
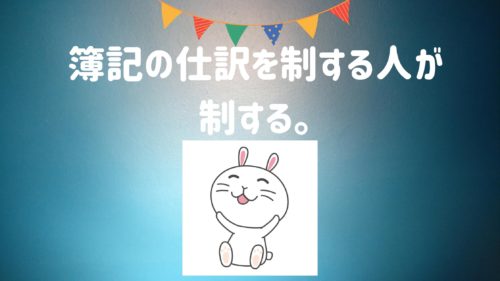
仕訳が覚えられないときのコツはこちら!
- 5分類のどれに属するか反射的にわかるレベルになる
- 覚えにくい仕訳や勘定科目は工夫して覚えること
- 毎日仕訳をする(最低5問)
- 人に説明する
- 耳から覚える
- 寝る前にテキストの基本仕訳をさらっと見る
順番に解説します。
5分類のどれに属するか反射的にわかるレベルになる
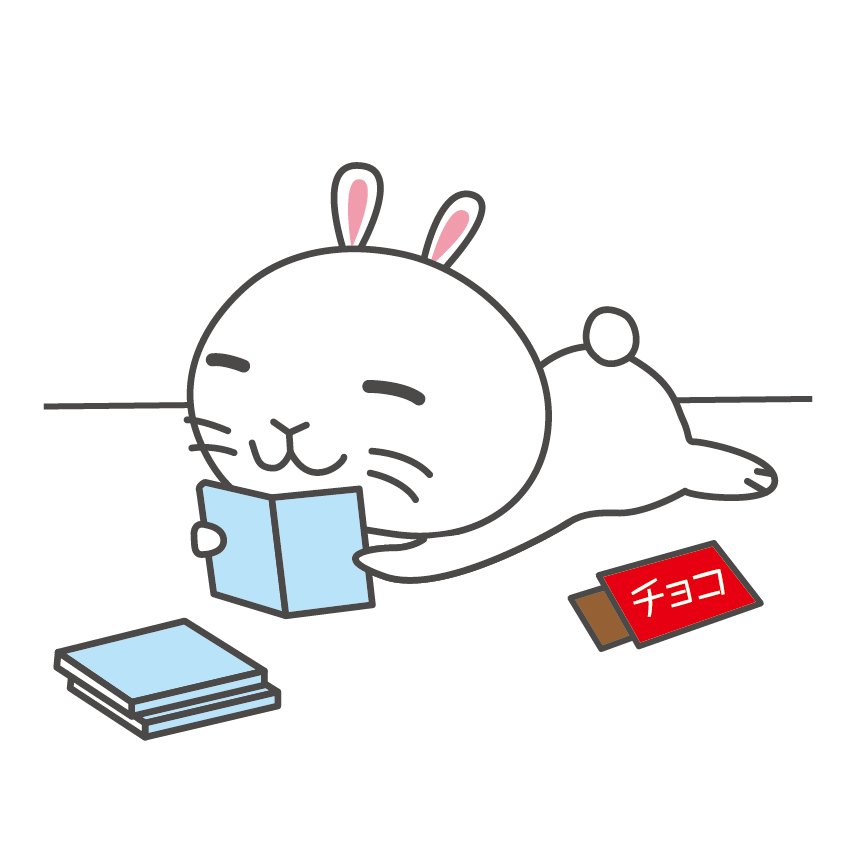
5分類って??
簿記の5つの分類といえば、以下の5つ。
・資産
・負債
・純資産
・費用
・収益
勘定科目は基本的に5つのうちのどれかに当てはまります。
仕訳が得意な人は、勘定科目を見た瞬間、反射的に5分類のどれに属する勘定科目なのか頭に浮かびます。

「りんご」と聞いて「果物」と浮かぶくらい無意識・反射的に!
その反面、仕訳が覚えられない方、仕訳が苦手な方は、勘定科目を見たあと、次にどこに分類されるのか考える時間と労力がかかります。
「売上割引」⇒「収益?費用?どっちだっけ?」⇒「費用だよね?」とこんなふうに。
しかし、仕訳が得意な人は、「売上割引(費用)」と一つの塊として頭に浮かびます。

仕訳を覚えるには、条件反射的に分類が判断できるぐらいになるのが理想。
5分類のどれに属するか反射的にわかるレベルになるには?
勘定科目を5つの分類に分けて覚えることは、「クローゼットに洋服を片付けるときのイメージ」に似ています。
下着や靴下、Tシャツ、長袖、羽織物などのいろんなタイプの洋服があるとします。
似ている性質のもの同士、同じ引き出しに入れますよね。
はじめは引き出しの中を確認して入れていきますが、慣れれば引き出しの中身を確認しなくても、次々洋服を入れて片付けていくことができます。

勘定科目を貸借対照表・損益計算書の5つの引き出しに片付け・整理をするイメージ!

じゃあ、反射的にできるレベルになるにはどうしたらいいの?そこが問題何だって!
個人的に効果があった方法としては…
A4用紙に「貸借対照表」「損益計算書」を記入。
テキスト・問題集で新しい勘定科目が出て来るたびに書き込んでいく方法。
書き込んだA4の紙は常に持ち歩いてスキマ時間に確認します。

ノートではなくA4の紙というのがポイント!
常にポケットに入れておけるサイズというのがスキマ時間がぴったりなんです。
また紙一枚にまとまっていると映像としての記憶も残りやすいです。
慣れてくると、書き込まなくても自然と覚えることができますが
仕訳ができない、仕訳が覚えられない、仕訳がごちゃごちゃと悩んでいる方は一度やってみてください。
どの勘定科目が、どの引き出し(5つのの分類)に入っているのか
一目瞭然なので、頭の中がスッキリ整理されますよ。
それによって、仕訳もスムーズに覚えられるというわけです。
覚えにくい仕訳や勘定科目は工夫して覚えること
簿記の勉強を始めると、簡単に覚えられる仕訳と、毎回悩んだり間違えたりする仕訳が出てきますよね。

そうそう、毎回悩む仕訳は同じ。
でも大丈夫です。
覚えにくい勘定科目・仕訳はみんな覚えられないところです。
とはいえ、無視できないので、なんとしてでも工夫して頭に入れましょう~!
覚えにくい勘定科目や仕訳を覚えるには?
覚えにくい勘定科目や仕訳を覚えるためには、
- 毎日仕訳をする(最低5問)
- 人に説明する
- 耳から覚える
- 寝る前にテキストの基本仕訳を流し見(毎日)
この4つを意識するといいですよ。

全部実際私がやってきたことだよ。
毎日仕訳をする(最低5問)
毎日、必ず仕訳問題を解くようにします。
残念ながら、突然仕訳ができるようになるなんていう魔法みたいなことはないわけなので、コツコツ必ず毎日仕訳をします。
簿記の勉強開始したばかりの頃は基本的な仕訳問題。
一通り回してからは過去問(または実践問題)の第一問を解きます。
私のおすすめは最低でも簿記検定第一問と同じ5問は毎日解くこと!
座って勉強できないスキマ時間、外出している時、通勤中の時間等でも、頭の中で仕訳をするようにしてみてください。

頭の中で借方〇〇貸方〇〇と浮かぶレベルを目指そう!
人に説明する
簿記2級はなんとなく書いたら合っていたというレベルの理解でいると、当日難易度が高い問題が出た場合対応できないことがあります。
自分がきちんと理解しているかどうかは、「人に説明できるかどうか」でわかります。
実際に誰かに聞いてもらう必要はありません。
人がいるという前提で壁に向かってブツブツ独り言のように、仕訳の方法を解説してみてください。
実際声に出して勘定科目を言うことで、記憶にも残りやすくなります。

人に説明してみると理解が弱い部分があからさまにわかりますよ。
耳から覚える
簿記2級になってくると、勘定科目も増え、更に長くて覚えにくい勘定科目も多くなってきます。
紙に書き、声に出して言ってみるの他に、耳から覚えるのも有効です。
簿記2級の勘定科目は、
「その他有価証券評価差額金」
「繰延税金資産」
「法人税等調整額」
「非支配株主に帰属する当期純損益」
「非支配株主持分当期変動額」など…長くて覚えにくいですよね。
簿記講座などを利用している場合、
自然と耳から入ってくる情報も多く、自然に勘定科目が覚えられます。
実際、私はお風呂・家事の最中、スタディング簿記講座を流していました。
自然と勘定科目が頭に入ってきて、長い勘定科目や仕訳を覚えるのが辛いという感覚はそれほどありませんでした。

\誰でもすぐ体験できる/
しかし、完全独学になると、テキスト、問題集の活字をジーッと見て書くだけの場合が多くなります。
それではどうしても覚えるまでに時間がかかります。
なかなか勘定科目や仕訳が覚えられないという方は、耳から覚えるという手段を使ってみるのもおすすめです。
寝る前にテキストの基本仕訳を流し見(毎日)
これも必ず、毎日やっていたことです。
布団の上で、テキストに載っている基本仕訳を15分程度の時間で一気に流し見するようにしていました。
ひとつずつ、じっくり考えたりせず、流し見です。
寝る前に記憶することで、睡眠中に記憶定着することはよく知られています。
私は、全体をさらっと見るようにしていましたが、自分の苦手な仕訳や勘定科目だけでも寝る直前に見るようにしてみてください。

記憶に定着しやすくなりますよ。
簿記の仕訳が覚えられないときのアドバイスのまとめ
ということで、仕訳が覚えられないときのアドバイスは、下記のとおりです。
- 5分類のどれに属するか反射的にわかるレベルになる
- 覚えにくい仕訳や勘定科目は工夫して覚えること
- 毎日仕訳をする(最低5問)
- 人に説明する
- 耳から覚える
- 寝る前にテキストの基本仕訳を流し見
仕訳を制する人が簿記を制する!これは本当です。
仕訳がスムーズになればなるほど、正確に早く解くことができるようになりました。
いきなり仕訳ができるようになることは無いですが、コツコツ毎日仕訳をすることで必ず仕訳が覚えられます!
勉強に活かせそうなところは、ぜひやってみてくださいね。